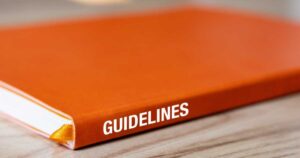いぬ
いぬ事務所ビルのオーナーです。フロアを賃貸するにあたり、設備の小規模な修繕は賃貸人の負担にしたいと思っているのですが、賃貸借契約を締結するにあたり注意すべきことはありますか。
さいたま未来法律事務所(埼玉県さいたま市浦和区)の弁護士佐々木康友です。
不動産オーナーや管理会社の皆様にとって、賃貸借契約(建物賃貸借契約)において、修繕義務をどこまで賃借人に負担させるかは、非常に悩ましい問題ではないでしょうか。
近年は、物件管理の効率化やコスト削減の観点から、「なるべく修繕費用を賃借人に負担してもらいたい」という要望が強まる傾向があります。しかし、民法の規定や裁判例を踏まえると、すべての修繕義務を一律に賃借人へ転嫁することはリスクが伴います。
例えば、賃貸借契約書に「修繕費用は全て賃借人が負担する」と記載したとしても、実際に裁判になった場合、その条項がそのまま有効と認められるとは限らないのです。特に、経年劣化や通常の使用による損耗については、賃貸人(オーナー)の負担とするのが原則であり、これを賃借人に負担させる特約は、場合によっては無効とされるリスクがあります。
本記事では、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法も踏まえ、実際の裁判例を取り上げながら、建物賃貸借契約における修繕義務のポイントやトラブルを避けるための実務対応策を解説します。
- 修繕義務に関する民法上の基本ルール
- 賃借人に修繕義務を負担させる特約の有効性
- 実際のトラブル事例と裁判所の判断
- 実務上の注意点と契約書作成のポイント
- 令和2年改正民法による影響
「自分の契約書が本当に有効なのか」「裁判所で無効とされるリスクはないのか」と不安をお持ちのオーナーや管理会社の方の参考になれば幸いです。
なお、建物賃貸借契約における修繕義務全般については、こちらの記事を参考にしてください。


修繕義務に関する民法の基本ルール
まず、賃貸借契約における修繕義務の基本を民法上の条文で確認しましょう。令和2年の民法改正後も、以下の点は大きく変わっていません。
民法の原則規定
まず、賃貸借契約における修繕義務の基本を民法上の条文で確認しましょう。令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法では、以下の規定が適用されています。
民法606条(賃貸人による修繕等)
1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人(オーナー)が、建物を通常使用するために必要な修繕を行う義務を負うというのが原則です。ただし、改正により、賃借人の責任で修繕が必要になった場合は例外とすることが明文化されました。
民法607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
② 急迫の事情があるとき。
改正民法では、賃貸人が修繕義務を履行しない場合に、賃借人自身が修繕できる場合が明文化されました。これは従来の判例法理を条文化したものです。しかし、改正民法においても、修繕義務は原則として賃貸人にあるという基本的な考え方は維持されています。
民法の基本的な考え方
これらの条文からわかるように、民法の基本的な考え方は、修繕義務は賃貸人(オーナー)にあるというものです。これは、賃貸借契約の本質が、賃貸人が賃借人に物件を使用・収益させる義務を負い、賃借人がその対価として賃料を支払うという関係にあることに由来します(民法601条)。
賃料には通常、物件の修繕費用も含まれていると考えられており、経済的に見ても、修繕費用は賃貸人が賃料収入によってまかなうことが想定されています。賃貸人は、賃貸借契約の存続期間中、賃借人が賃貸物件を円滑に使用収益できる状態を維持する義務を負っており、そのためには、物件に生じた破損や不具合を修繕する必要があるというわけです。
特約が有効となるための要件
民法の基本的な考え方は、修繕義務は賃貸人(オーナー)にあるというものですが、一方で、民法には契約自由の原則(民法521条)があり、当事者間の合意によって特約を設けることも可能です。そのため、「修繕義務を賃借人に負担させる」という特約自体は、原則として有効となり得ます。
しかし、賃貸人の修繕義務は、賃借人が安心して賃貸物件を利用するための重要な要素となっています。したがって、この義務を特約によって賃借人に転換させる場合には、その有効性や範囲について慎重な検討が必要となります。
例えば、以下のような場合には特約が無効とされる可能性もあります。つまり、契約書に「修繕は全て賃借人負担」と書いてあるからといって、その条項が必ず有効とは限らないのです。
- 特約があまりにも一方的で、賃借人に過度な負担を課す場合
- 特約の内容が明確でない場合
- 消費者契約法などの強行法規に反する場合
- 公序良俗(民法90条)や信義則(民法1条2項)に反する場合
そこで、特約により、どこまで有効に修繕義務を賃借人に負担させられるのかが問題になります。この判断は、物件の性質(住居用か事業用か)、賃借人の属性(個人か法人か)、賃料の設定、特約の内容や説明の程度など、様々な要素を総合的に考慮して行われますが、基本的には以下の点に留意する必要があると考えられます。
特約の必要性・合理性
まず、特約の必要性や客観的合理性が求められます 。例えば、賃料が相場よりも大幅に安く設定されている代わりに、賃借人が一定範囲の修繕を行うことを合意している場合などが考えられます。
何の合理的な理由もなく、一方的に賃借人に不利な特約は、無効とされる可能性が高くなります。特に、通常の賃料を徴収しながら、建物の主要構造部分の修繕義務まで賃借人に負担させるような特約は、その合理性を欠くと判断される可能性があります。
賃借人の認識
賃借人が特約の内容を明確に認識し、その存在と内容について十分な理解していることも重要です 。賃貸借契約締結時には、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、修繕義務に関する特約の内容が賃借人に対して丁寧に説明する必要があります 。
曖昧な説明や契約書に小さく記載されているだけでは、賃借人が特約の内容を十分に理解したとはいえず、無効とされる可能性があります。
賃借人の意思表示
賃借人が特約による義務を負担する意思表示をしていることも必要です 。単に契約書に特約が含まれているだけでなく、賃借人がその内容を理解し、納得した上で、特約について合意していることが求められます。
賃借人の負担が大きくなったり、内容が複雑な場合などは、特約部分に賃借人の署名や捺印を別途求めるなど、明確な合意があったことを示す証拠が必要となることもあるでしょう。
特に、賃借人が個人の場合、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされます (消費者契約法10条)。したがって、賃貸人の修繕義務を全面的に免除し、賃借人に一切の修繕義務を負担させるような特約は、消費者契約法に違反し無効とされる可能性が高いです 。判例においても、「入居後の大小修繕は賃借人がする」という特約は、賃貸人の修繕義務を免除する趣旨に過ぎず、賃借人に積極的な修繕義務を課すものではないと解釈される傾向があります 。
賃借人が負担する修繕の範囲
賃借人に修繕義務を負担させる特約が存在する場合、具体的にどのような範囲が修繕が賃借人の負担となるのかが問題となります。修繕の種類によって、その負担の範囲は大きく異なる可能性があります。
修繕の規模
まず修繕の規模が問題となります。
小修繕
一般的に、電球や蛍光灯の交換、水道のパッキンや給水栓の取り換えなどの小修繕については、賃貸人の承諾なしに賃借人の負担で行うことができるという特約が多くの賃貸借契約に採用されており、裁判例でもその有効性が認められています 。これらの小修繕は、費用が比較的安価であり、日常生活における消耗や軽微な損傷に対応するものであると考えられます。しかし、何が小修繕に該当するのかについては、契約書において具体的に明記しておくことが望ましいでしょう 。修理金額が概ね1万円以下の場合は小修繕の範囲と考えることができるという見解もあります 。
大規模修繕
一方、建物の屋根、壁、柱などの躯体部分や、給排水設備、電気設備などの主要な設備に関する大規模修繕については、原則として賃貸人がその義務を負うと考えられています 。たとえ特約で賃借人に修繕義務を負担させる旨が定められていたとしても、建物の構造に関わるような大規模な修繕まで賃借人に負担させることは、特別の事情がない限り認められないとする裁判例があります 。このような大規模修繕は、建物の維持保全に不可欠であり、その費用も高額になることが多いため、賃借人に一方的に負担させることは、消費者保護の観点からも問題視される可能性が高いです 。
経年劣化・通常損耗または故意・過失
経年劣化や通常損耗による修繕なのか、賃借人の故意・過失によって生じた損傷による修繕なのかも問題となります。
経年劣化・通常損耗
経年劣化や通常損耗による修繕については、原則として賃貸人が責任を負うべきであると考えられています 。これらは、賃借人が通常の用法に従って賃貸物件を使用していれば避けられない損耗であり、その修繕費用は賃料に含まれていると解釈されるのが一般的だからです。特約によってこれらの修繕義務を賃借人に負担させる場合には、その旨が明確に定められている必要があり、消費者契約法などの観点からその有効性が厳しく判断されることになります 。国土交通省のガイドラインにおいても、経年劣化や通常損耗による修繕は原則として賃貸人の負担とされています 。
故意・過失
一方、賃借人の故意や過失によって生じた損傷については、賃借人が修繕義務を負うのが原則です 。例えば、不注意で窓ガラスを割ってしまった、壁に故意に穴を開けてしまったなどの場合は、賃借人がその修繕費用を負担する必要があります 。民法606条1項但書の規定もこの考え方に基づくものと思われます。ただし、この場合も、何が賃借人の故意・過失によるものなのかを明確にしておくことが紛争予防のために重要となります。
以上を表にまとめると、次のように整理できると思います。
| 修繕の種類 | 原則的な負担者 | 特約による変更の可否 | |
|---|---|---|---|
| 修繕の規模 | 小修繕(電球、パッキン交換など) | 賃貸人 | 可能(一般的) |
| 大規模修繕(躯体、主要設備など) | 賃貸人 | 困難(原則として無効) | |
| 経年劣化・ 通常損耗 | 経年劣化・通常損耗 | 賃貸人 | 可能(明確な合意が必要) |
| 賃借人の故意・過失 | 賃借人 | 変更なし | |
賃借人と賃貸人との間で発生しうる紛争事例
賃借人に修繕義務を負担させる特約が存在する場合、賃借人と賃貸人との間で様々な紛争が発生する可能性があります。特に、修繕の必要性の判断、修繕範囲の解釈、費用負担の割合などが紛争の種となりやすいです。
漏水に関する紛争
漏水に関する紛争は頻繁に発生する事例の一つです 。例えば、上階からの漏水が発生した場合、その原因が建物の老朽化によるものなのか、上階の住人の過失によるものなのかで、修繕義務を負うべき者が異なります。また、漏水によって賃借人の家財が損害を受けた場合、その損害賠償を誰に請求できるのかという問題も生じます。賃貸人が修繕義務を怠ったために、賃借人が損害を被ったとして、損害賠償や賃料減額を求めるケースも少なくありません 。
エアコン・給湯器等の設備機器
エアコンや給湯器などの設備機器の故障も、よくある紛争の原因です 。これらの設備が契約時に備え付けられていた場合、通常は賃貸人が修繕義務を負いますが 、特約によって賃借人が負担することになっている場合や、故障の原因が賃借人の過失によるものとされた場合には、費用負担を巡って争いが生じやすくなります。特に、設備の老朽化による故障なのか、賃借人の不適切な使用によるものなのかの判断が難しい場合、紛争が長期化する傾向があります。
床の損傷
床の損傷に関する紛争も多く見られます 。例えば、フローリングの傷や凹みが、通常の使用によるものなのか、賃借人の故意や過失によるものなのかで、原状回復義務の範囲や修繕費用を負担すべき者が異なります。家具の設置による跡や、物を落としたことによる傷などは、通常損耗とみなされることが多いですが、ペットによる傷や、重量物を長期間置いていたことによる凹みなどは、賃借人の負担とされる場合があります。
賃貸物件の居住性に関わる問題
建物の全体的な老朽化や、居住に必要な設備の不具合など、賃貸物件の居住性に関わる問題についても、賃貸人と賃借人の間で紛争が生じることがあります 。賃貸人が必要な修繕を行わない場合、賃借人は賃料の支払いを拒否したり、契約の解除を求めたりすることがあります 。また、賃借人が自ら修繕を行った場合に、その費用を賃貸人に請求できるかどうかも争点となることがあります 。
賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は自ら修繕を行い、その費用を賃貸人に請求できる場合があります 。民法改正により、賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合や、急迫の事情がある場合には、賃借人が修繕できることが明文化されました 。しかし、自己判断で修繕を行う場合には、事前に賃貸人に通知することが原則であり、事後の費用請求が認められないケースもあるため注意が必要です 。
原状回復義務に関する問題
修繕義務に関連する事項として、賃貸借契約終了時の原状回復義務を巡る紛争も頻繁に発生します 。何が通常損耗に該当するのか、どこまでを賃借人が原状回復すべきなのかについて、賃貸人と賃借人の間で意見が対立することが少なくありません。特に、ハウスクリーニング費用や、畳、襖、クロスなどの交換費用を巡っては、特約の有効性も含めて多くの紛争が生じています 。
賃借人に修繕義務を負担させる特約に関する裁判例
賃借人に修繕義務を負担させる特約の有効性については、多くの裁判例が存在し、裁判所は個別の事案に応じて特約の有効性を判断しています。代表的な裁判例をいくつかご紹介します。
以上の裁判例を分析すると、裁判所は、特約の文言の明確性、特約締結に至る経緯、賃料の額、建物の状態、修繕の種類、賃借人の認識と合意の有無など、様々な要素を総合的に考慮して特約の有効性を判断していることがわかります。特に、住宅の賃貸借においては、消費者保護の観点から、賃借人に過度な負担を課す特約は厳しく判断される傾向にあると言えるでしょう。
最高裁昭和43年1月25日判決
「入居後の大小修繕は賃借人がする」という特約の解釈が争われた事案です。本判決では、この特約は単に賃貸人が民法606条1項の修繕義務を負わないという趣旨に過ぎず、賃借人が家屋使用中に生ずる一切の汚損、破損箇所を自己の費用で修繕し、目的家屋を当初と同一状態で維持すべき義務を負うものではないと解釈しました。
重要なのは、特約の文言が曖昧な場合、賃借人に過度な負担を課すものとは解釈しないという裁判所の姿勢です。本特約は、賃貸人の修繕義務を免除するものではあっても、賃借人が自己の費用で修繕し、目的家屋を当初と同一状態で維持すべき義務まで負うわけではないとしています。
この判決からは、①特約の文言が明確でない場合は限定的に解釈される、②修繕義務免除特約と修繕負担特約は区別して考える必要がある、③賃借人に修繕義務を負わせる場合は明確かつ具体的な合意が必要である、という重要な指針が得られます。曖昧な修繕特約を定める場合、賃貸人が意図したほど広範な義務を賃借人に課せない可能性があることに留意すべきです。
東京高裁昭和59年10月30日判決
ゴルフ練習場の賃貸借契約で「経営上必要とする一切の経費は賃借人の負担とする」という特約があった事案です。練習場のネット支柱(鉄柱)が倒壊した際、その修繕義務の所在が争われました。
本判決では、特約の文言だけでなく、建物や設備の性質、修繕の内容にも着目し、包括的な費用負担の特約でも、すべての修繕義務が賃借人に転嫁されるわけではないとしました。特に、恒久的な構造物である鉄柱の維持・補修については、特約があっても賃貸人の責任であると判断しています。
この判決からは、賃借人に修繕義務を負担させる特約がある場合でも、①建物の本質的・構造的部分に関わる修繕、②多額の費用を要する修繕、③恒久的な構造物の修繕については、明確かつ具体的な特約がない限り、賃貸人の義務として解釈される傾向があることがわかります。包括的な文言による修繕義務の転嫁には限界があり、特約の内容・範囲は合理的に解釈される点に注意が必要です。
名古屋地裁平成2年10月19日判決
専用部分の修理や小修繕を賃借人負担とする特約(修理特約)の解釈が争われた事案です。賃貸借契約書には「専用部分についての修理、取替(畳、ふすま、障子、ガラス、照明器具、スイッチ、壁、床、その他の外廻り建具を含む建具、浴槽、風呂釜(バーナーを含む)、その他の小修理)は、賃借人の負担において行う」との特約がありました。
本判決では、集中給湯方式における温水器(電気温水器)の取替えが特約の対象となるかが争点となりました。裁判所は「温水器はかなり長期の使用を予定して設置されるものであり、取替費用も高額で、集中給湯方式という建物の品等にかかわる設備である」と認め、さらに賃料額や敷金の取り扱いも考慮し、温水器は本修理特約の対象には含まれないと判断しました。
この判決は、修繕負担特約があっても、①長期使用を予定した設備、②取替費用が高額な設備、③建物の基本的性能に関わる設備の修繕・交換については、特約の対象外と解釈される可能性が高いことを示しています。修繕特約で賃借人に負担させるのは「小修繕」に限定され、多額の費用がかかる主要設備の修繕まで賃借人に負担させるには、より明確かつ具体的な特約条項が必要であることを示唆しています。
東京地裁平成25年12月19日判決
賃借人修繕負担特約の有効性が消費者契約法の観点から争われた事例です。本判決では、「修繕費等のうち、例えば、当該建物の主要な構造部分の修理費等のように、一般的に、当該修繕によって賃借人が賃借する期間を超えて賃貸人の利益となるようなもので、かつ、多額の費用を要する修繕費等の支出についてまで賃借人の負担とすること」は、消費者契約法10条に反して無効になると判断しました。
この判決は、賃借人が消費者である場合、修繕負担特約の有効性を消費者保護の観点から厳格に判断する傾向を示しています。特に、①建物の主要構造部分の修繕、②賃借期間を超えて賃貸人の利益となる修繕、③多額の費用を要する修繕を賃借人に負担させることは、消費者の利益を一方的に害する条項として無効とされる可能性が高いことを示唆しています。
消費者契約における修繕特約を設ける際には、消費者契約法の規制を考慮し、賃借人に過度な負担を課さないよう注意する必要があります。この判決は、修繕特約の有効性が契約の性質(事業用か居住用か)や賃借人の属性(事業者か消費者か)によっても異なることを示した重要な事例です。
実務上の注意点と対策
修繕義務に関する裁判例を踏まえ、実務上どのような点に注意すべきか、具体的な対策を見ていきましょう。
修繕の内容を具体的かつ明確にする
まず、特約の内容は具体的かつ明確に記載することが重要です 。どのような種類の修繕が賃借人の負担となるのかを具体的に列挙し、曖昧な表現は避けるべきです 。特に、小修繕と大規模修繕の範囲を明確に区別し、経年劣化や通常損耗に関する責任についても具体的に定めることが望ましいです。
それぞれの修繕について、誰がどのような責任を負うのかを明確に定めておくことが重要です。特に、以下の点に注意しましょう。
小修繕の範囲を明確にする
電球交換、蛍光灯の交換、水道のパッキン交換など、日常的で費用が少額なものは賃借人負担としても無効とされるリスクは低いです。しかし、小修繕の範囲を明確に定義しておくことが重要です。「修理金額が1万円以下のもの」といった記載が考えられます。
設備機器の経年劣化に関する扱いを明記する
エアコン、給湯器、配管設備などは耐用年数や故障原因をめぐって紛争になりやすいので、個別に記載するのが望ましいでしょう。「製造から○年経過した設備機器の修理・交換は賃貸人負担」といった記載が考えられます。
通常損耗と賃借人の過失の区別を明確にする
例えば、壁の傷一つとっても「通常使用による擦り傷」と「不注意による深い傷・穴」では責任の所在が異なります。判断基準をできるだけ明確にしておくことが紛争予防につながります。
賃貸人と賃借人の公平な負担割合
修繕義務を賃借人に負担させる特約は、どうしても一方的な内容になりがちです。そこで、賃貸人が負担すべき部分も明確に示し、賃貸人と賃借人の負担割合をバランスが取れている形にしておくと、裁判所でも有効性が認められやすくなると思います。例えば、賃料を相場よりも低く設定する代わりに、一定範囲の修繕を賃借人に負担させるなどの合理的な理由がある場合には、特約の有効性が認められやすくなります。
例えば次のような記載が考えられます。
- ○○については賃借人が、△△については賃貸人が修繕費用を負担する
- 小修繕(1万円以下の修繕)は賃借人負担、それ以上の修繕は賃貸人負担とする
- 賃借人の故意・過失による損傷は賃借人負担、経年劣化・通常損耗による損傷は賃貸人負担とする
また、賃料や敷金の設定が、修繕リスクを考慮した金額であるなどの事情があると、特約の合理性を裁判所に訴える材料になる場合があります。例えば、相場より低い賃料設定であることを契約書に明記しておくといった工夫も考えられます。
入居時の状態確認と記録
契約締結時には、物件の状態を詳細に記録しておくことが重要です。入居時の写真やチェックリストなどを活用し、既存の傷や汚れを明確にしておくことで、退去時の原状回復義務に関する紛争を未然に防ぐことができます。特に次の点の確認と記録は重要となるでしょう。これらの確認と記録は、後日のトラブル防止のための「保険」と考えるべきです。
- 入居前の写真撮影
- 賃借人立会いの下での物件確認
- チェックリストへの賃借人のサイン
- 既存の不具合や損傷の明記
賃借人に対する十分な説明と理解を得ること
賃借人に対して特約の内容を十分に説明し、理解と同意を得ることが不可欠です 。賃貸借契約締結時には、重要事項説明において、修繕義務に関する特約の内容を口頭で丁寧に説明するだけでなく、書面でも明確に提示し、賃借人が質問する機会を設けるべきです 。場合によっては、特約部分に賃借人の署名や捺印を別途求めることも有効です。特に、通常と異なる負担を賃借人に求める場合は、その内容を理解・納得してもらった上で契約を締結することが、後々のトラブル防止につながります。
- 修繕負担の区分を視覚的に示す(表やイラストを用いる)
- 具体的な事例を挙げて説明する
- 質問の機会を十分に設ける
- 説明内容を書面でも残しておく
日頃のコミュニケーション・管理体制を大切に
契約書の文言だけでなく、オーナーや管理会社の実際の対応も争点となることがあります。老朽化が進んでいるのに放置していた、報告を受けても対応が遅かったなどの事実があれば、裁判所は賃貸人の修繕義務違反を認定しやすくなってしまいます。
日頃から定期点検や連絡体制を整え、賃借人が早めに相談・報告しやすい雰囲気を作っておくことが、長期的には紛争予防につながります。賃借人からの修繕依頼や報告があった場合は、迅速に対応し、対応記録を残しておくことも重要です。
トラブルを未然に防ぐために
建物賃貸借契約における修繕義務の問題は、オーナー・管理会社の皆さまにとって避けて通れないテーマです。「契約書に書いてあるから大丈夫と思っていたのに、いざ裁判になってみたら無効とされてしまった:という例は少なくありません。
トラブルを未然に防ぐためには、以下の点に注意することをお勧めします。
契約書作成・レビュー
賃借人の属性(個人・法人、事業用・居住用など)や物件の状況を踏まえ、「どこまで負担してもらうか」を慎重に検討しましょう。無効リスクを最小限に抑えつつ、オーナーの意向を最大限反映できる条項を作ることが重要です。
定期的な物件点検と記録
定期的に物件の状態を確認し、必要な修繕を先送りにせず適切に実施することが、長期的には大きなトラブルを防ぐことにつながります。点検記録を残しておくことも重要です。
賃借人とのコミュニケーション
入居中も賃借人と良好な関係を維持し、小さな不具合や修繕ニーズに早めに対応することで、大きなトラブルを未然に防げることが多いです。
専門家への相談
契約書の作成・見直し時や、実際にトラブルが生じた際には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士のアドバイスを受けておけば、後々の大きな紛争を防ぐことができます。
不動産賃貸は大きな投資と収益が絡むビジネスです。修繕義務をめぐるトラブルで資産価値が下がったり、紛争コストが増大したりするのは避けたいところです。
修繕義務に関するよくある質問
最後に、不動産オーナーや管理会社から多く寄せられる質問にお答えします。
- 賃借人が勝手に修繕を行った場合、その費用は請求できるのでしょうか。
-
原則として、賃借人が賃貸人に事前の通知なく勝手に修繕を行った場合、その費用を賃貸人に請求することはできません。ただし、民法607条の2により、以下の場合は賃借人が自ら修繕を行い、費用を請求できる可能性があります。
- 賃借人が賃貸人に修繕の必要性を通知し、または賃貸人がその必要性を知っていたにもかかわらず、相当期間内に修繕を行わなかった場合(同条1号の場合)
- 急迫の事情がある場合(水漏れが激しく、放置すれば被害が拡大する場合など)(同条2号の場合)
ただし、この場合でも、賃借人が行った修繕が必要かつ相当なものであることが前提となります。過度に高額な修繕や、必要以上に豪華な設備への交換などは、費用請求が制限される可能性があります。
- 経年劣化と賃借人の故意・過失による損傷を区別するには。
-
これは実務上、非常に判断が難しい問題です。一般的には、以下のような基準が考えられます。
- 経年劣化の例
日光による壁紙の変色、通常の使用による床材の摩耗、製品の寿命に達した設備の不具合など - 賃借人の故意・過失の例
タバコの焦げ跡、明らかな衝撃による大きな傷・凹み、通常ではあり得ない使用方法による破損など
判断が微妙なケースも多いため、入居時と退去時の状態を写真等で記録しておくことが重要です。また、国土交通省の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」なども参考になります。
- 経年劣化の例
- 設備機器(エアコン、給湯器など)の修繕・交換は誰の負担になりますか。
-
原則として、賃貸物件に元々備え付けられていた設備機器の修繕・交換は賃貸人の負担です。ただし、以下のような場合は例外となる可能性があります。
- 賃借人の故意・過失による破損の場合
- 小修繕特約がある場合(高額な修理・交換は通常は賃貸人負担)
- 契約書に明確に賃借人負担と定められており、その特約が有効と認められる場合
実務上は、特約があったとしても、耐用年数を超える設備機器の故障については賃貸人負担、賃借人の明らかな過失による故障はとされることが多いでしょう。
- 事業用物件と居住用物件で修繕義務の考え方は異なりますか。
-
事業用物件の方が特約の有効性が広く認められる傾向があります。事業用物件では、以下の理由から修繕義務を賃借人に負担させる特約が有効とされる範囲が広いと考えられています。
- 事業者間の契約であり、個人消費者保護の要請が弱い
- 賃借人の交渉力が居住用に比べて強い場合が多い
- 事業用物件では、賃借人の業種に合わせた特殊な内装・設備が施されることが多い
ただし、事業用物件であっても、建物の基本構造や主要設備の経年劣化に関する修繕まで賃借人に負担させることは、裁判で無効とされるリスクがあります。
- 共用部分の修繕は誰の負担になりますか。
-
共用部分(廊下、階段、エレベーター、外壁など)の修繕は、原則として賃貸人の負担です。共用部分は全ての賃借人が利用するものであり、特定の賃借人だけに修繕義務を負わせることは適切ではないとされています。
おわりに
修繕義務をめぐる問題は、賃貸経営において非常に重要なテーマです。できるだけ修繕費用を抑えたいオーナーの希望は理解できますが、法的リスクを考慮せずに過度に修繕義務を賃借人に転嫁することは、長期的には大きなトラブルの原因となりかねません。
本記事で解説したように、裁判所は「修繕義務は原則として賃貸人にある」という民法の基本原則を重視する傾向にあります。特に、通常損耗や経年劣化に関する修繕費用を賃借人に負担させる特約は、その有効性が厳しく判断される可能性が高いことを忘れないでください。
適切な修繕対応は、物件の資産価値の維持向上につながるだけでなく、賃借人との良好な関係の構築、空室リスクの軽減、そして長期的な経営安定にも寄与します。
不動産経営においては、目先のコスト削減だけでなく、長期的な視点で物件価値を維持・向上させる戦略が重要です。そのためには、適切な修繕計画の策定と実行、そして賃借人との明確なコミュニケーションが欠かせません。
埼玉県さいたま市浦和区のさいたま未来法律事務所では建物賃貸借に関するトラブルの解決に力を入れています。修繕義務に関する判断に迷った際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
個々の物件状況や契約内容に応じた、最適なアドバイスを提供させていただきます。皆様の賃貸経営が、トラブルなく安定して続くことを心より願っております。