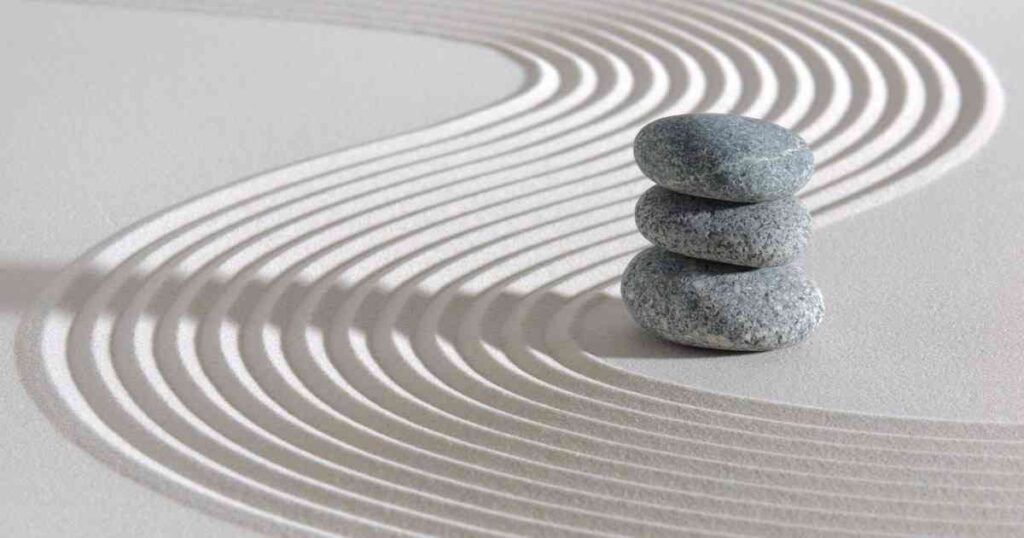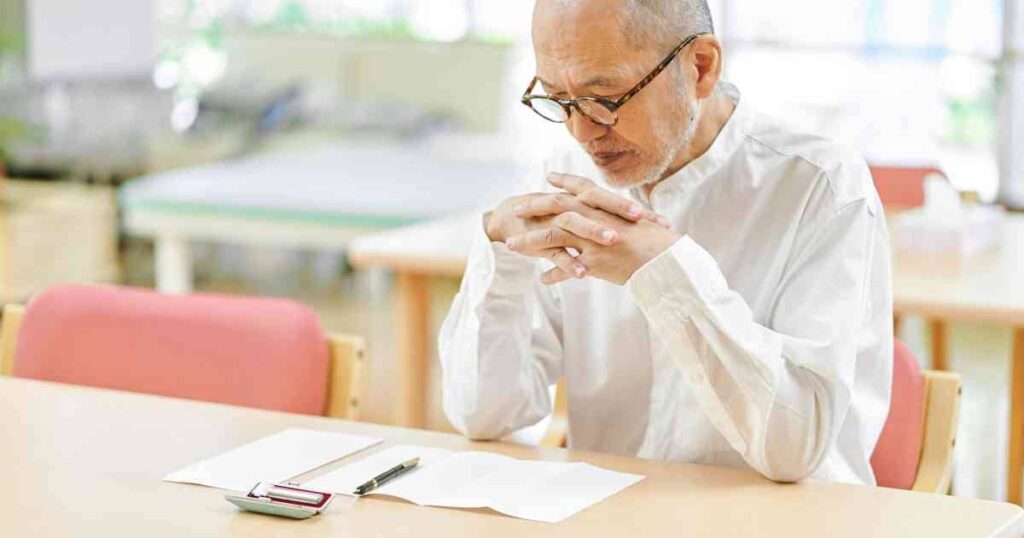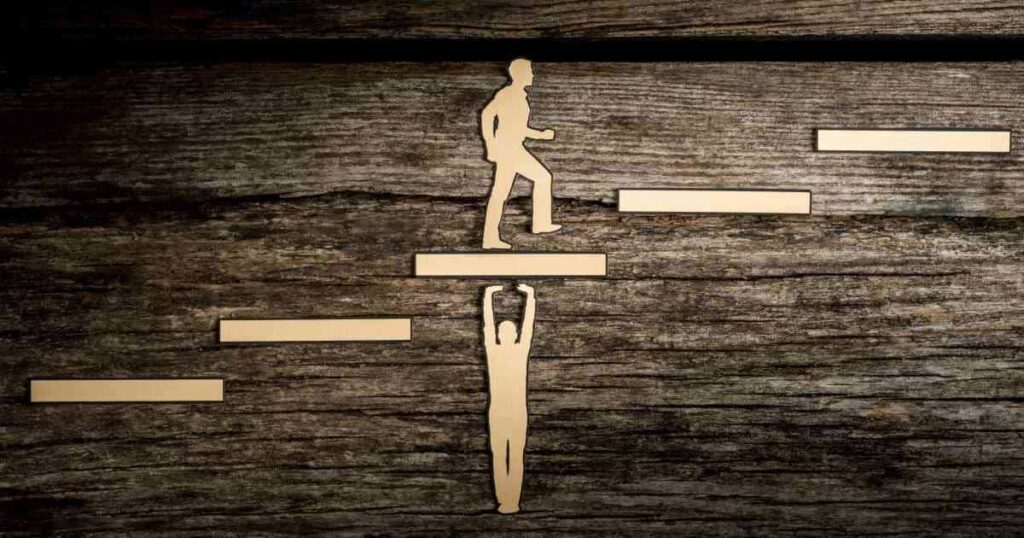遺言・相続– category –
-

【弁護士が解説】配偶者の老後を守る!民法903条4項の持ち戻し免除推定規定とは
「夫が亡くなった後の私の生活が心配…」「自宅を妻に生前贈与したが、相続で問題にならないだろうか…」 このような不安や心配を抱えていらっしゃる方は少なくありません。今回は、配偶者の老後の生活を守るために2018年の民法改正で新設された、特別受益の... -

【弁護士が解説】遺言執行者の権限・報酬などについてわかりやすく説明します
遺言執行者について知りたい人「私に何かあった時のために遺言書を作成しようと思います。所有している不動産の一つを兄の子に遺贈したいと思っています。知人からは、相続人以外に財産を遺贈するなら、遺言で遺言執行者を指定しておいた方がよいとアドバ... -

【弁護士が解説】遺言とは何かについて説明します~遺言書が無効とならないために最低限知っておくべきこと
遺言について知りたい人「私に何かあった時のことを考えて遺言書を作ろうと思います。思ったことを自由に書いてしまってもいいのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。ある人の死後、家族に宛てた手紙が発見されることがあります。病床において、家族に... -

【弁護士が解説】遺産分割手続きの全体的な流れについてわかりやすく説明します
遺産分割について知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私を含めた子どもだと思いますが、父は再婚しているので私たちの知らない相続人がいるかもしれません。どのように手続きを進めていけばよいでしょうか。」 弁護士の佐... -

【弁護士が解説】後継ぎ遺贈と受益者連続信託について説明します~孫やひ孫に財産を承継させるには
後継ぎ遺贈と受益者信託について知りたい人「我が家には先祖代々守り続けてきた土地があります。現在は私が所有者ですが、私が死んだら長男に全ての土地を受け継がせ、さらに長男の死後も長男の子に全ての土地を受け継がせたいです。こういったことを遺言... -

【弁護士が解説】条件付遺贈と期限付遺贈についてわかりやすく説明します
条件付遺贈・期限付遺贈について知りたい人「先日、孫の一人が結婚して、お祝いとして私が結婚資金を出しました。他の孫が結婚した時にも結婚資金を援助したいと思います。私が死んだ後も、孫が結婚した時に私の財産から結婚資金を援助できるようにしたい... -

【弁護士が解説】遺贈とはなにか~包括遺贈と特定遺贈についてわかりやすく説明します
遺贈について知りたい人「私に何かあったときのために遺言を作ろうと思います。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があると聞きましたが何が違うのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。遺贈とは、遺言者が遺言によって、他人に自分の財産を与える行為をいいま... -

【弁護士が解説】負担付遺贈とはなにかについてわかりやすく説明します~遺贈を受けたら無限に負担しないといけないのか
負担付遺贈について知りたい人「妻は身体が不自由で介護が必要です。これまでは施設には入れずに私が介護しています。私に何かあった後は、長男に私の全財産を遺贈する代わりに、妻を高齢者介護施設に入所させ、十分な介護サービスを受けさせてもらうよう... -

【弁護士が解説】死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します
死因贈与と遺贈の違いを知りたい人「私が死んだら、先祖代々の土地と建物は弟に譲ろうと思います。死因贈与という方法があるそうですがどのようなものなのでしょうか。また、遺言で遺贈する場合とは何が違うのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。自分... -

【弁護士が解説】遺産分割前に相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しをする方法について説明します
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々...