 ねこ
ねこ遺言の撤回はできるのか知りたい人「私は5年前に市役所に財産を寄付する公正証書遺言を作成したのですが、考えが変わったので遺言を撤回したいと思います。どのようにすればよいでしょうか。」
弁護士の佐々木康友です。
遺言が効力を生ずるのは遺言者の死亡時です。
一度遺言が作成されても、遺言者が死亡するまでの間に事情が変わって、遺言者が遺言をなかったことにしたい(遺言の撤回)と思うことは十分にあり得ます。
その場合、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。
それではどのように遺言は撤回すればよいのでしょうか。また、遺言を撤回すると遺言の効力はどうなるのでしょうか。
今回は一旦作成した遺言を撤回するにはどうすればよいかわかりやすく説明します。
- 遺言の撤回とは何か
- どのような場合に遺言の撤回ができるのか
- 遺言を撤回するとどうなるのか
- 遺言の撤回を取り消すことはできるのか
遺言の撤回とは
遺言とは
遺言とは、民法に定める方式に従って、遺言者の最終意思を表示したものです(民法960条)。
民法の定める方式に従って遺言が作成されることにより、遺言者の死亡時に、遺言に書かれたとおりに遺言者の最終意思が効力を生じます(民法985条1項)。
遺言撤回の自由
遺言者によって、遺言が作成される時期は様々です。
遺言者の亡くなる直前に作成される場合もあれば、遺言が作成された後、遺言者が死亡するまで、相当の長期間となることもあります。
当然、その間に遺言者の考えが変わり、遺言をなかったことにしたいと思うこともあるでしょう。
それなのに、一度作成された遺言は撤回ができないこととなると、遺言者の最終意思は実現されません。
そこで、遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
民法1022条(遺言の撤回)
民法 – e-Gov法令検索
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
撤回する権利は放棄できない
一方で、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできません(民法1026条)。
例えば、
- 遺言において遺言を撤回する権利を放棄する旨を定める
- 遺贈する相手(受遺者)との間で遺言を撤回しない旨の合意する
といったことをしても無効です。
遺言は、遺言者の最終意思であるため、遺言者の真意に基づいて作成される必要があります。
遺言を撤回する権利を放棄することを認めてしまうと、遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄したばかりに、遺言を撤回することができず、真意に基かない内容の遺言が効力が生じることにもなりかねません。
そこで、遺言者が、いつでも遺言を撤回して、真意に基づく遺言を作成できることを保障するために、遺言を撤回する権利を放棄することを禁じているのです。
民法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法 – e-Gov法令検索
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
撤回は遺言の方式に従う必要がある
遺言は民法に定める方式に従って作成されなければなりません(民法960条)。
それだけ厳格な方式に基づいて作成されたものですので、遺言を撤回する場合にも、遺言の方式に従う必要があります(民法1022条)。
つまり、遺言の撤回自体についても、遺言として行う必要があります。
したがって、受遺者に対して、遺言を撤回する旨の内容証明郵便を送付するなどしても、撤回は認められませんので注意が必要です。
なお、遺言の方式に従いさえすればよいので、前の遺言と撤回の遺言の方式が異なっていても構いません。
例えば、前の遺言が公正証書遺言(民法969条)で作成され、撤回の遺言が自筆証書遺言(民法968条)で作成されるといったことも認められます。
遺言の撤回の擬制
これまで述べたのは、遺言者が、明確な意思により遺言を撤回する場合です。
これに対し、遺言者の意思にかかわらず、遺言者が一定の行為をした場合、遺言を撤回したとみなされることがあります。
以下に、その場合を説明します。
抵触する遺言
Aは、「Xに甲土地を譲る」との遺言を作成した後、「Yに甲土地を譲る」との遺言を作成した。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
民法1023条1項(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法 – e-Gov法令検索
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
ここでいう「抵触する」とは、前の遺言と後の遺言が両立しない場合を意味します。
これは、前の遺言と後の遺言の内容が客観的に両立し得ない場合だけでなく、前の遺言と両立させない趣旨で後の遺言が作成されたと評価される場合も含まれます。
上のケースでは、後の遺言の「Yに甲土地を譲る」は、前の遺言の「Xに甲土地を譲る」に客観的に抵触しますので、前の遺言を撤回したものとみなされます。
抵触する法律行為
Aは、「Xに甲土地を譲る」との遺言を作成した後、Yに甲土地を贈与した。
抵触する遺言の場合と似ていますが、遺言者が、生前に、遺言と抵触する財産処分その他の法律行為を行った場合にも、遺言は撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
法律行為とは、意思表示によって、権利義務の発生や消滅などの効果を発生させるものをいいます。売買契約が典型例です。
民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法 – e-Gov法令検索
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
ここでいう「抵触する」とは、前の遺言と後の財産処分その他の法律行為が両立しない場合を意味します。
これは、客観的に両立し得ない場合だけでなく、前の遺言と両立させない趣旨で後の法律行為が行われたと評価される場合も含まれます。
前の遺言と両立させない趣旨で後の法律行為が行われたと評価される場合としては、例えば、次のような場合が考えられます。
Aは、Xに対し「養子になってくれるなら全財産を譲る」と申し出たところ、Xはこれに応じた。そこで、Aは、Xと養子縁組の上、「Xに全財産を遺贈する」との遺言を作成した。しかし、その後関係が悪化し、AとXは離縁した。
上のケースでは、Xに全財産を遺贈する遺言をすることと、AとXが離縁することは、それ自体を見れば、必ずしも客観的に両立しえないものではありません。
しかし、そもそも、XがAに全財産を遺贈する遺言を作成したのは、Aが、Xと養子縁組をしたことが前提であったので、AとXが離縁した以上、XがAに全財産を遺贈する遺言を撤回する趣旨であると考える考えるのが合理的であるということになります(最高裁判例昭和56年11月23日)。
「原審の適法に確定した前記一の事実関係によれば、Dは、上告人らから終生扶養を受けることを前提として上告人らと養子縁組したうえその所有する不動産の大半を上告人らに遺贈する旨の本件遺言をしたが、その後上告人らに対し不信の念を深くして上告人らとの間で協議離縁し、法律上も事実上も上告人らから扶養を受けないことにしたというのであるから、右協議離縁は前に本件遺言によりされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたものというべきであり、したがつて、本件遺贈は後の協議離縁と抵触するものとして前示民法の規定により取り消されたものとみなさざるをえない筋合いである。」
最高裁判所判例昭和56年11月13日(民集35巻8号1251頁)
また、遺言と抵触する法律行為は、遺言者自身がした場合に限り、撤回したものとみなされます。
- 遺言者の成年後見人(法定代理人)が財産処分した
- 遺言者の債権者が遺言の目的財産を競売にかけた
といった場合には撤回はされません。
遺言書の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
また、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です(民法1024条)。
民法1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
ここで遺言書を「破棄」するとは、
- 遺言書をビリビリに破く
- 黒塗りにして読めないようにする
- 日付だけを消していつ作成されたものか分からなくする
など様々なパターンが考えられますが、どのような場合に「破棄」があったとするかは、具体的な基準があるわけではありません。
なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されています。
遺言者の手元にあるのは正本であり、必要があれば何度も交付されるものですから、これを破棄しても遺言を撤回したものとはみなされません。
公正証書遺言は破棄ができない遺言ということになります。
したがって、遺言書の破棄が問題となるのは、主として自筆証書遺言(民法968条)の場合となります。
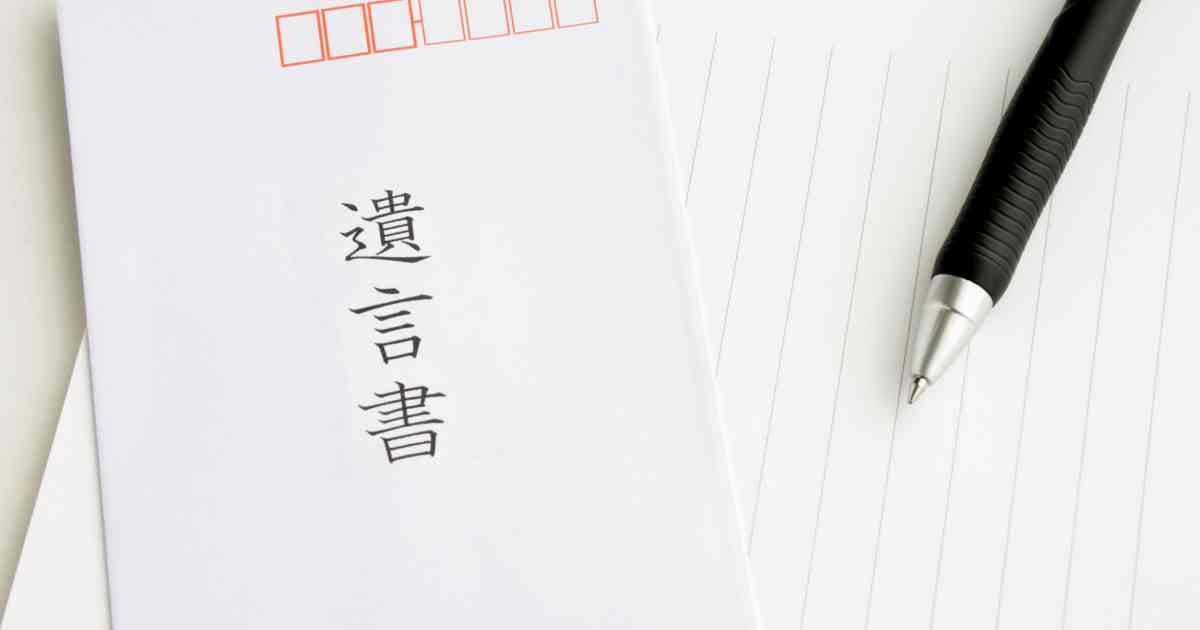
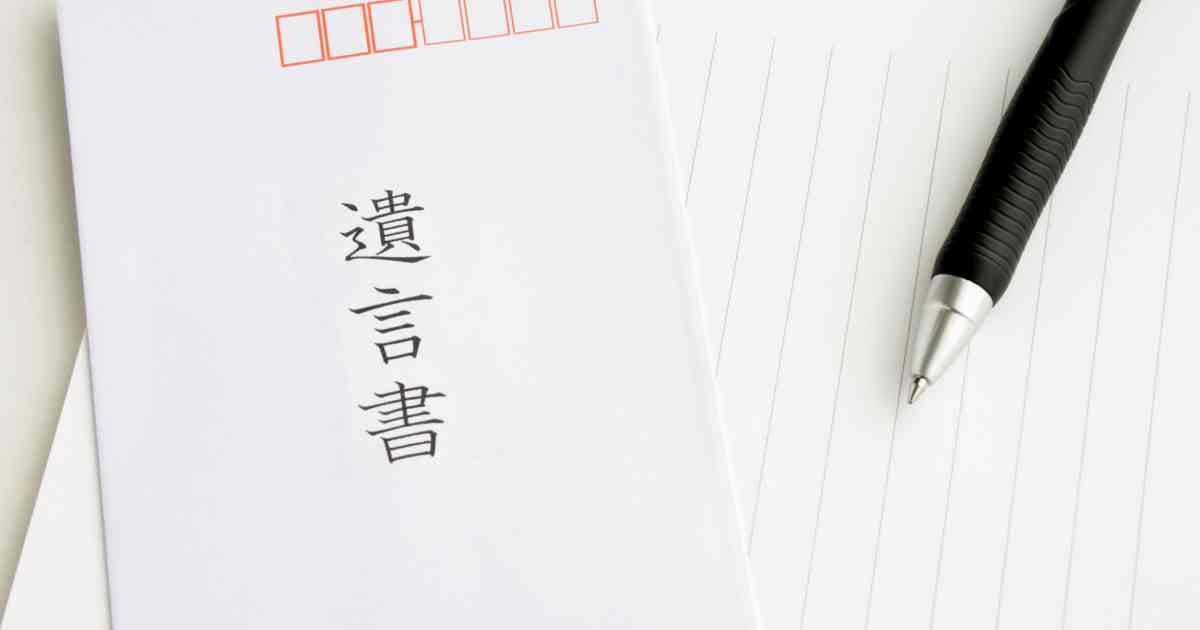
Aが死亡した。Aの自筆証書遺言が発見されたが、遺言書には、文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた。
こういったケースの場合、遺言書の破棄(民法1024条)であるのか、自筆証書遺言の加除訂正(民法968条3項)であるのかが問題となります。
同様の事件で最高裁判所の判例平成27年11月20日(民集69巻7号2021頁)では次のとおり述べられています。
「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
最高裁判所判例平成27年11月20日(民集69巻7号2021頁)
以上によれば、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。」
最高裁判所の判例では、具体的にこういった行為をすれば「破棄」になるというような基準は示されておらず、「その行為の有する一般的な意味に照らして」判断すると、遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であると判断しています。
したがって、「破棄」といえるかどうかは、個別具体的に行為の一般的な意味から考えていくしかありません。
その行為から「破棄」したとはいえない場合は、自筆証書遺言の加除訂正(民法968条3項)の問題となり、加除訂正の要件を満たしていない場合は、遺言は当初の内容どおりということになります。
一部撤回の場合
Aは、「Xに甲土地と乙建物を譲る」との遺言を作成した後、Yに甲土地を贈与した。
撤回の対象は遺言の全体だけでなく、一部の場合もあります(民法1022条)。
その場合、遺言の残りの部分の効力がどのようになるかは、その遺言と撤回の内容によって異なります。
上のケースでは、「Yに甲土地を贈与する」ことと、「Xに乙建物を譲る」という遺言は両立しえますので、「Xに乙建物を譲る」ことについては遺言の効力は維持されるものと考えられます。
撤回行為を撤回した場合
遺言の撤回行為がさらに撤回されても、元々の遺言の効力は復活しないのが原則です(民法1025条)。
遺言者が撤回行為を撤回しても、元々の遺言の効力を復活させる意思があるとは限りませんし、遺言者の死後に意思を確認することもできないからです。
但し、錯誤、詐欺又は強迫により遺言が撤回されていた場合は、撤回行為を撤回すると元々の遺言の効力が復活します(民法1025条但書)。
民法1025条(撤回された遺言の効力)
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
Aは、昭和62年12月6日、甲遺言をした。Aは、平成2年3月4日、乙遺言をした。乙遺言には、「甲遺言はその全部を取り消します」との記載があった。さらに、Aは、平成5年11月8日、丙遺言をした。丙遺言には、「乙遺言は全て無効とし、甲遺言を有効とする」との記載があった。
ケースと同様の事件で、最高裁判例では、次のとおり、撤回行為の撤回により元々の遺言の効力が復活すると示しました。
つまり、撤回行為の撤回により、元々の遺言の効力を復活させる遺言者の意思が明確である場合は、遺言者の最終意思を尊重するべきと判断されたものと考えられます。
「遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」
最高裁判例平成9年11月13日
まとめ
今回は、遺言の撤回はどのように行えばよいのかについて説明しました。
遺言の撤回は、民法に定められた遺言の方式に従って行うことが原則となりますが、前の遺言と抵触する遺言を作成したり、法律行為をした場合も撤回したものとみなされます。
また、遺言を破棄した場合も、撤回したものとみなされます。
遺言の撤回は、民法に従って適切に行わないと、遺言者にとっては想定しない結果にもなりかねません。
遺言の撤回をしたい場合は、弁護士等の専門家に相談した方が無難だと思います。








