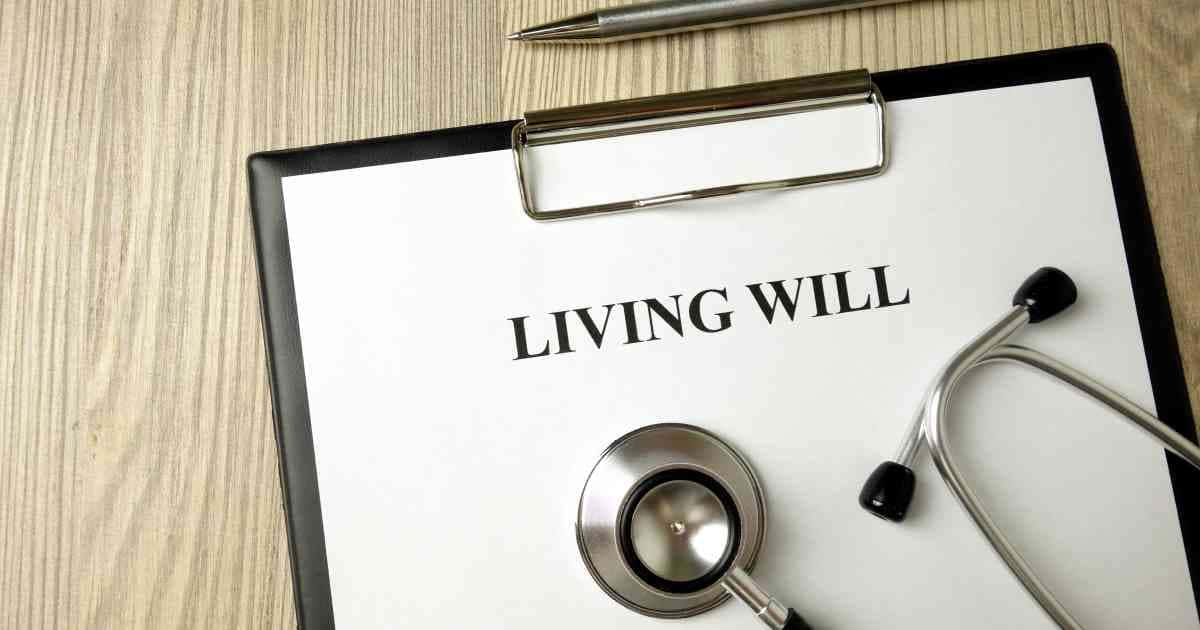ねこ
ねこ遺言書の検認手続きについて知りたい人「父が亡くなりました。封印された遺言書があります。遺言書は勝手に開封してはいけなくて、家庭裁判所の検認手続きが必要と聞きましたが、どのような手続きなのでしょうか。」
弁護士の佐々木康友です。
今回は、遺言書の検認手続きについてわかりやすく説明します。
遺言書を発見したらまずは検認手続きが必要
被相続人が亡くなった後、被相続人の遺品のなかから、遺言書が発見されることがあります。
被相続人から、生前、相続人が遺言書を預かっていることもあります。
その遺言書が封筒に入れられて、封印されていたとします。
封印は、遺言書が封筒に入れられていて、封をした証拠として押印されていることをいいます。
この場合、遺言書を所持している相続人は、開封して中身を確認してよいのでしょうか。
また、中身を確認したら、遺言書の内容のとおり、すぐに銀行などで手続きができるのでしょうか。
答えはどちらもできません。
まずは、家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の検認手続きを受けなければなりません(民法1004条)。
家庭裁判所に遺言書を提出することを怠ったり、遺言書を所持している人が自分で遺言書を開封してしまったりすると過料5万円が科されることになります(民法1005条)。
また、遺言書を改ざんしたり、隠したりすると、そもそも相続人としての資格を失うことにもなります(相続人の欠格事由。民法891条5号)。
検認手続きの目的は遺言書の偽造・変造の防止
それでは検認手続きが求められているのでしょうか。
それは、遺言書の改ざんの防止のためです。
遺言書の方式のうち公正証書遺言については、検認手続きが不要とされています(民法1004条2項)。
これは、公正証書遺言については、原本が公証役場に保存されており、遺言者の死後、相続人が遺言を改ざんすることは不可能だからです。
これに対し、他の方式、特に自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、遺言書を発見した相続人が簡単に改ざんを行うことも可能となります。
そこで、民法では、まずは改ざんされる前の遺言書の状態を確認するため、遺言書を所持している相続人に対し、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出するように求めているのです。
但し、自筆証書遺言については、法務局に遺言書の原本を保管することができます。
この制度を活用した場合には改ざんを行うことは難しくなりますので、自筆証書遺言であっても検認手続きは不要となります(遺言書保管法11条)。
検認手続きの必要な遺言は
上でも説明しましが、公正証書遺言は検認手続きが必要ありません(民法1004条2項)。
それ以外の方式の遺言は検認手続きが必要になります。
但し、自筆証書遺言については、法務局に遺言書の原本を保管した場合は、検認手続きは不要となります(遺言書保管法11条)。
検認手続きの実際
それでは、検認手続きの流れを一通り説明しておきましょう。
検認申立書の提出
まず、遺言を所持している人が家庭裁判所に検認申立書を提出します。
遺言書がある場合、家庭裁判所で検認をしてもらわないと相続手続きが何もできません。
申立手続きの概要は次のとおりとなります。
申立人
- 遺言書を保管している人
- 遺言書を発見した相続人
申立先
- 遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所
管轄の家庭裁判所を調べたい方はこちらを参照してください。
手数料
- 遺言書(封筒の場合は封筒ごと)1通につき、収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
相続人の数、家庭裁判所によって変わるので、管轄の家庭裁判所に問い合わせてください。 - 検認手続き終了後、検認済証明書を発行してもらうことができますので、収入印紙150円分と印鑑を用意しておくとよいでしょう。
必要書類
- 検認申立書
裁判所のホームページからダウンロードできます。 - 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(遺言者との親族関係がわかるもの)
- 遺言者の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
その他、相続人によっては追加で必要となる戸籍謄本がありますので、家庭裁判所に問い合わせをしてください。
例えば、兄弟姉妹のみが相続人となる場合、配偶者、子及びその代襲者、直系尊属がすべて亡くなっていることを戸籍謄本で示す必要が出てきます。
つまり、兄弟姉妹が相続人であることを証明するため、先順位の相続人が死亡していることを戸籍謄本で証明する必要があるのです。
検認期日の通知
無事に書類が受理されると、しばらくして家庭裁判所から相続人全員の住所に通知があります。
遺言書の検認申立てがなされたということと、検認手続き(検認期日)を行う日が決まったので出席してくださいというものです。
この時点で、遺言書が存在することを初めて知る相続人も多いです。
申立人が出席しないと検認期日が開けないので、検認期日は申立人の都合を踏まえて決められます。
他の相続人に対しては一方的に検認期日が通知されます。
申立人以外の相続人が欠席する場合はどうなるのか気になるところですが、結論としては出席は義務ではありません。
任意です。申立人さえ出席すれば、検認手続きは進められます。
出席できなかった相続人は、後日、家庭裁判所に検認調書のコピーの申請ができます。
そこに遺言書のコピーも添付されていますから、遺言書や検認手続きの内容を知ることができます。
検認手続きに欠席すると、後日の遺産分割手続きで何か不利なことにならないか心配される方もいるかもしれませんが、その点は心配ありません。
検認手続きは、あくまでも遺言書の存在を確認するものでしかありませんので、遺言内容については立ち入って判断することはありません。
検認期日当日
申立人は、遺言書を持参します。
申立人は、遺言書を持参します。
遺言書が封印されている場合は、裁判官が開封します。
相続人があらかじめ開封することは許されません(民法1004条3項)。
裁判官、裁判所書記官、申立人、他の相続人が一つの部屋に集まって手続きが開始されます。
出席者に対しては、裁判官から氏名・住所の確認があります。
申立人が所持している遺言書を裁判官に手渡します。
裁判官は、遺言書が封印されている場合は、ハサミで開封します。
裁判官が遺言書の状態を確認していきます。
茶色の封筒に入っていて・・・黒のボールペンで手書きで書かれていて・・・日付は・・・署名・押印は・・・なとど裁判官が遺言書の方式で定められている点について確認していき、裁判所書記官が裁判官の発言を書き留めていきます。
遺言書で重要なのは、遺言書に署名している本人が書いたものかどうかということです。
つまり筆跡が問題となります。
そのため、裁判官から、出席者に対して、筆跡は本人のものかどうか質問されます。
質問に対しては、素直な意見を述べればよいと思います。
実際は、遺言者の筆跡は見慣れていたはずなのに、いざ遺言書を見てみると本人の筆跡かよくわからないということが多いです。
少しでも不安な場合は、わからないと答えておけばよいと思います。
それで、不利になることはありません。
検認期日後
検認期日当日、申立人に遺言書が返還されます。
あわせて、検認済証明書の申請を行います。
これがないと、銀行や法務局に名義変更の申請をしても受け付けてもらえません。
検認済証明書には「この遺言書は、平成〇年〇月〇日に検認されたことを証明する」といった文言が記載されています。
検認手続きに立ち会わなかった相続人には、後日、家庭裁判所から検認済通知書が送られます。
必要があれば、家庭裁判所に検認調書のコピーの発行を申請することができます。
検認済証明書とは、家庭裁判所で遺言書の検認が行われたことを証明する文書です。
検認手続きの効果は
検認手続きは、遺言書の改ざんを防止するため、遺言書の状態を確認するものです。
検認手続きのなかでは、手書きで書かれているか、日付が書かれているか、遺言者の署名・押印があるかなど、民法で定められた遺言の方式に合致しているかについて、ひとつずつ確認されていきます。
しかし、あくまでも方式についてひとつずつ確認していくだけです。
結果として、その遺言が有効かどうかについてまでは判断しません。
例えば、遺言作成当時、遺言者には遺言能力がなかったとして、遺言が無効となることはあり得ます。
もし、遺言の有効性を争いたいならば、別途、調停や裁判なのに訴える必要があります。
ここはとても重要な点なので注意しましょう。
まとめ
今回は遺言書の検認手続きについて説明しました。
遺言書の検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄の家庭裁判所となりますので、相続人が離れた場所に住んでいる場合は手間が掛かります。
公正証書遺言であれば、検認手続きは不要ですし、自筆証書遺言でも、法務局の遺言書保管制度を利用すれば不要となります。
遺言書は、あくまでも遺言者の意思によって作成されるものであるため、相続人としてはそれに従うしかありませんが、遺言書が作成されていることがあらかじめ分かっている場合は、遺言者にこれらの手続きを進めてみるのもよいでしょう。