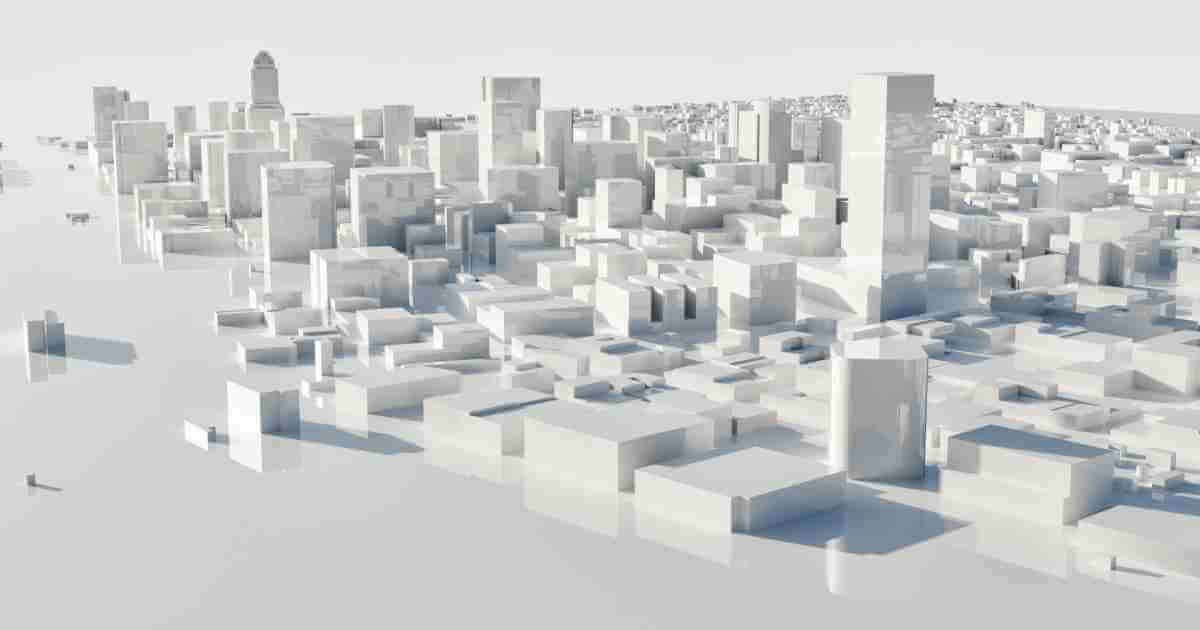ねこ
ねこ事業用定期借地権の中途解約について知りたい人「事業用定期借地権で土地を貸す予定です。借主は、いつでも中途解約できるようにしたいと言っていますが、貸主としては、突然中途解約されるのは困ります。どういった契約内容にすればよいでしょうか。」
弁護士の佐々木康友です。
今回は、事業用定期借地権を中途解約する場合についてわかりやすく説明します。
地主(借地権設定者)・借対権者が、事業用定期借地権を一方的に中途解約することはできません。
中途解約するには、当事者間で合意するか、あらかじめ契約に中途解約条項を設けておく必要があります。
ただし、事業用定期借地権を中途解約する場合には、いつ・どのような条件で中途解約できることとするのか、違約金は支払うのか、借地上の建物の買取りをどうするのかなど検討すべきことが多くあります。
今回は、事業用借地権を中途解約する場合についてわかりやすく説明します。
この説明を参考に適切な内容の中途条約条項を設けて頂けたら幸いです。
- 事業用定期借地権とは
- 事業用定期借地権は中途解約できるのか
- 貸主・借主どちらからもできるのか
- 中途解約条項の内容は
- 違約金は定められるのか
事業用定期借地権とは
本記事では、借地権設定者のことを貸主、借地権者のことを借主として説明しています。
事業用定期借地権とは、借地借家法23条に規定されている定期借地権です。
一定期間の経過により借地契約は確定的に終了し、借地権が消滅します。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 借地権の存続期間 | 10年以上50年未満 1項事業用定期借地権:30年以上50年未満 2項事業用定期借地権:10年以上30年未満 |
| 建物の用途 | 事業用に限定 |
| 性質 | 普通借地権には認められてる次の効力が発生しない 借地契約が更新しない(借地借家法5条) 建物の再築による借地期間の延長がない(借地借家法7条) 建物買取請求権がない(借地借家法13条) |
なお、事業用定期借地権は、借地権の存続期間の違いから、次の2つに分かれています。
借地権の存続期間のほか、性質に違いはありません。
| 名称 | 借地権の存続期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 1項事業用定期借地権 | 30年以上50年未満 | 借地借家法23条1項 |
| 2項事業用定期借地権 | 10年以上30年未満 | 借地借家法23条2項 |
事業用定期借地権全般についてはこちらで詳しく説明していますので参考にしてください。


事業用定期借地権は中途解約できるのか
借地権者(借主)からの中途解約
- 借地上の建物が火災により滅失した
- 経営不振により、事業を撤退せざるを得なくなった
事業用定期借地権は数十年の長期に及ぶので不安定な部分が多々あります。
例えば、上記のような事態が生じた場合に、借主は、事業定期借地権設定契約を中途解約することはできないのでしょうか。
中途解約ができないと、借主は無用の地代・賃料を支払い続けることとなり大きな経済的負担となるため問題となります。
まず、貸主(借地権設定者)と借主(借地権者)で合意ができれば中途解約できるのは当然のことです。
問題となるのはその合意ができない場合に、借主の方から一方的に中途解約の申入れはできるのかということです。
借地借家法では、定期建物賃貸借については、やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃貸借の解約の申入れができることとされています(借地借家法38条5項)。
一方、事業用を含めた定期借地についてはこのような条文は設けられていません。
そうすると、原則として借主から一方的に中途解約の申入れをすることはできないと考えざるを得ません。
それでは、借主が事業用定期借地権を中途解約する方法はないのかというと、そのようなことはありません。
事業用定期借地契約の締結にあたり、中途解約権を留保する特約(中途解約条項)を定めてさえおけば、借主が中途解約することは可能となります。
借主としても、地代・賃料の負担の重さを考えれば、中途解約ができないとリスクが高すぎるとして契約を締結するのは困難となるでしょう。
貸主としても、後々の紛争を防ぐ観点から、一定の要件の下では中途解約を認める特約を定めておく必要性があるものと考えられます。
借地権設定者(貸主)からの中途解約
これに対し、貸主が中途解約できる特約を定めることは認められないと考えるべきです。
これを認めると、借主が大きな不利益を受けることになり、借主の保護を図る借地借家法の趣旨に反することとなるからです。
したがって、借地権設定者の中途解約権を留保する特約は無効となるものと考えられます。
民法618条、これが準用する同法617条1項によれば、貸主についても中途解約権を留保することができそうにも思えますが、借地借家法の趣旨からすればやはり認められないと考えられます。
事業用定期借地権設定契約の中途解約条項の内容
事業用定期借地権設定契約の締結にあたり、中途解約権を留保する特約を定めておけば、借主が中途解約することは可能となります。
それでは、中途解約条項としてはどのような内容が考えられるのでしょうか。
貸主と借主の利益は相反する関係にあります。
中途解約条項を定めるには、貸主と借主の合意が必要なのですから、契約の目的に応じてバランスの取れた内容にする必要があります。
具体的には、中途解約条項の内容を定めるにあたっては、次のような内容を考慮していくことになります。
- 中途解約の理由
- 契約終了の時期
- 違約金設定の有無
- 権利金返還の必要性
- 建物の買取りをするかどうか
以下、検討すべきポイントを説明します。
どのような場合に事業用定期借地権設定契約を中途解約できることにするのか
まず、どのような場合に事業用定期借地権設定契約を中途解約できるのかを決める必要があります。
任意に中途解約の申入れができることとすると、貸主としては不安定な状態に置かれることになりますので、一定の要件を設けるのが通常です。
- 自然災害により建物が滅失したなど不可抗力による場合
- 経営不振等により事業を継続することができないなど借主の事情による場合
- 貸主が、第三者への借地権の譲渡を認めない場合
借主が、事業用定期借地契約を中途解約しなければならないのは様々な場合が考えられます。
やむを得ない事情により事業を継続することができない場合は、中途解約を認める必要性もあるものと思われます。
ただし、中途解約の理由によっては違約金を徴収することを検討するべきでしょう。
また、借地契約後すぐに中途解約されてしまうと、地代・賃料収入を見込む貸主の利益が大きく損なわれることになります。
そのため、借地契約後一定期間経過後でなければ中途解約ができないこととすることも考えられます。
例えば、中途解約権の発生について、次のような制約を設けることも考えられます。
- 事業用定期借地権の存続期間の半分の経過後
- 事業用定期借地権設定契約締結後10年経過後
上に述べた事情と期間の要件を組み合わせることもできますし、一定期間経過後は任意に中途解約の申入れができることにすることも可能です。
いつ事業用定期借地権が消滅するのか
借主が中途解約の申入れをして、すぐに事業用定期借地権設定契約が終了するというのは一般的ではありません。
通常は、数ヶ月程度の期間の猶予が設けられます。
- 借主が建物を解体するなどして原状回復するのに必要な期間
- 貸主が次の借主を募集するのに必要な期間
などを考慮する必要があるからです。
これらに要する期間を検討の上、事業用定期借地権設定契約の終了時期を決める必要があります。
契約終了までは地代・賃料の支払義務が発生するのが通常ですが、後々紛争とならないように、契約終了までの地代・賃料の支払いについても明確に規定しておくべきでしょう。
違約金の支払いを求めることはできるのか
これまで述べてきたように、そもそも、原則として、借主は、中途解約条項がない場合には、一方的な事業用借地権設定解約の中途解約の申入れをすることはできません。
貸主としては、土地を貸すことにより長期にわたって地代・賃料の収入を得られることを見込んでいます。
事業用定期借地権設定契約を中途解約することにより、この収入を得られなくなるのですから、貸主の経済的損失も考慮する必要があります。
そこで、貸主の経済的損失を補填するため、借主が、事業用定期借地権設定契約を中途解約した場合には、貸主に違約金を支払わなければならないとする特約を設けることも可能です。
中途解約した場合は違約金を支払うという特約を定めておかなければ、違約金を請求できないので、必ず特約を定めるように注意しましょう。
それでは、違約金の金額をどのくらいにすればよいのでしょうか。
長期にわたる契約期間である以上、予定どおりに契約期間を満了できないリスクは当然にあるのですから、そのリスクを貸主・借主がどのように分担するのかを検討する必要があります。
自然災害により建物が滅失し、事業用定期借地権の残存期間から建物を再築するのも困難となった場合には、貸主・借主がそれぞれ同等のリスクを負担するべきと考えられます。
一方、経営不振等により事業を継続することができないなど借主の事情による場合には、借主の方がより多くのリスクを負担するべきと考えられます。
つまり、中途解約の理由により違約金の金額を増減させることが考えられます。
具体的な違約金の金額の定め方ですが、地代・賃料の●ヶ月分といった定め方が考えられます。
この定め方の方が、中途解約の理由による違約金の金額の違いを反映させやすいと考えます。
事業用定期借地権設定契約が、借主の債務不履行を理由として解除がされた場合には、違約金の規定は適用されないのが通常です。
その場合には、借主の債務不履行によって発生した損害を計上して、損害賠償請求をすることになります。
権利金の返還は必要か
事業用定期借地権の設定にあたり、借主が貸主に権利金を支払っていることがあります。
権利金には次の性質があるといわれます。
- 定期借地契約を締結すること自体の対価
- 地代・賃料の一部
敷金・保証金と異なり、原則として、権利金については、事業用定期借地契約が終了しても返還する必要がありません。
ただし、契約期間の満了ではなく中途解約されたのであれば、地代・賃料の一部として権利金が支払われている場合には、残存期間に相当する分は返還するべきとも考えられます。
権利金を借地権設定の対価と考えるのであれば、中途解約であったとしても必ずしも返還の必要はないものと考えられます。
いずれにせよ、事業用定期借地権設定契約を中途解約した場合、権利金については問題となる可能性があるので、その取扱いについては明確に規定しておく必要があるといえるでしょう。
建物の買取りをするかどうか
事業用定期借地権の場合、借主に建物買取請求権(借地借家法13条)がありませんので、借地契約の終了後、借主は、建物を解体・撤去するなどして土地を原状回復して、貸主に返還する義務があります。
ただし、事業用定期借地権が消滅した場合に、貸主が建物を買い取る旨の特約をすることが妨げられるものではありません。
汎用性が高い建物で、の借主が見つかりやすい場合には、貸主が建物を買い取ることも考えられるでしょう。
その場合の買取価格は、建物買取請求権の場合の時価(借地借家法13条)が参考になるものと考えられます。


まとめ
今回は、事業用定期借地権を中途解約する場合について説明しました。
事業用定期借地権は数十年の長期に及ぶものなので、当然ながら不確定要素は多くならざるを得ません。
それでも、生じ得る問題はあらかじめ想定して契約書に定めておくことで、すべては難しいもののできるだけリスクを少なくするために配慮しておくことが必要です。
契約書に的確に表現するのは工夫を要する場合も多いので、弁護士等の専門家に相談するのも有益でしょう。