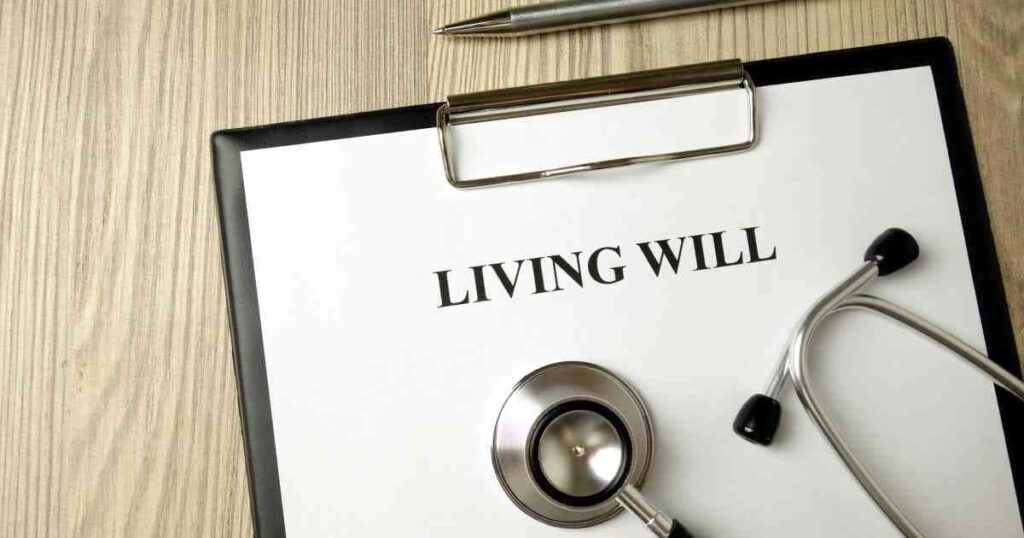-

【弁護士が解説】差押え(強制執行)により養育費を回収する方法についてわかりやすく説明します。
元夫が養育費を支払わないため強制執行で差押えをしたい人「離婚調停で養育費を支払う取り決めをしたのに、元夫が養育費を支払いません。強制執行で元夫の財産を差押えしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。家庭... -

【弁護士が解説】養育費の履行勧告の申出手続きについてわかりやすく説明します
養育費を支払わない相手に履行勧告する方法について知りたい人「元夫との間で養育費の調停が成立して、半年間は支払われましたが、先月から支払いがありません。できるだけ自主的に支払ってもらいたいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。」 弁護... -

【弁護士が解説】遺産分割前に相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しをする方法について説明します
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々... -

【弁護士が解説】預金・貯金(預貯金債権)の相続についてわかりやすく説明します
預金・貯金(預貯金債権)の相続について知りたい人「母が亡くなりました。父は先に亡くなっています。相続人は兄弟姉妹3人です。遺産は不動産と銀行預金がありますが、兄弟姉妹で揉めており、遺産分割には時間が掛かりそうです。それまで銀行預金の引き出... -

【弁護士が解説】相続放棄で3ヶ月の熟慮期間が過ぎたらどうするかについてわかりやすく説明します
相続放棄について知りたい人「父が亡くなりました。父は個人で事業をしていて、複数個所から借金をしていたようなのですが、詳細はわかりません。もし財産より借金の方が多ければ、相続放棄をしようと思うのですが、いつまでにしないといけないのでしょう... -

【弁護士が解説】遺留分侵害額請求権の計算手順を丁寧に説明します
遺留分侵害額請求権の計算手順を知りたい人「遺留分侵害額請求をしたいのだけど、どうやって計算すればいいのでしょうか。誰にいくら請求できるかもどうやって計算したらいいのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。これまでの業務経験を踏まえてこうい... -

【弁護士が解説】相続財産の調査方法についてわかりやすく説明します
相続財産の調査方法について知りたい人「父が急死しました。家族で遺産分割をしなければなりませんが、父の財産の状況が全く把握できていません。どのように調べたらよいのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。今回は、被相続人の相続財産の調査をする... -

【弁護士が解説】借地権の相続手続きにあたり注意すべきことをわかりやすく説明します
借地権の相続手続きについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。父は借地上に家を建てて住んでいました。遺言書で建物は私が相続することになっているのですが、借地権も私が相続するのでしょうか。また、借地権を相続するときは... -

【弁護士が解説】公正証書遺言がまるごとわかる~必要書類・効力・証人・手数料等について
公正証書遺言について知りたい人「遺言書を作ろうと思っています。知人から公正証書遺言であれば無効となることはないと聞きました。公正証書遺言にしておけば絶対大丈夫でしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。今回は公正証書遺言について説明します。遺... -

【弁護士が解説】遺言書の検認手続きについてわかりやすく説明します
遺言書の検認手続きについて知りたい人「父が亡くなりました。封印された遺言書があります。遺言書は勝手に開封してはいけなくて、家庭裁判所の検認手続きが必要と聞きましたが、どのような手続きなのでしょうか。」 弁護士の佐々木康友です。今回は、遺言...